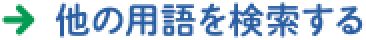ヴィニーズ・ワルツ(Viennese Waltz)
ウィンナ・ワルツとも書きます音楽は軽快な3/4拍子。基本リズムは123、123で1にアクセントがあります。競技会用のテンポは1分間に60小節くらい。競技会では決勝のみで踊られます。踊りの起源は1700年代の後半に南ドイツで作られ、農民たちがランドラーと呼ぶ速いテンポで回転する踊りが1800年台に全ヨーロッパとアメリカで広がったものと考えられています。ヴィニーズは英語で「ウィーン(人)の、ウィーン風の」の意味。ウィンナを広辞苑で引くと、英語の(Vienna)とドイツ語の(Wienna)が併記されています。どちらの発音も「ヴィエナ」ですが、ドイツ語綴りを日本人が英語読みしたところから「ウィーン」が出たのだと思われます。
・ヴィニーズ・ワルツは通常の教師用テキストにはなぜか載っていません。また、ヴィニーズ・ワルツの小冊子には7種類のフィガーしか記載されていません。1930年代の世界チャンピオン、ジョニー・ウェルズ&レニー・シソン(Jonny Wells and Renee Sissons)のHPには次のように書かれていました — 「1960年代に競技会で使われるべきヴィニーズ・ワルツのフィガー議論が英国とドイツの間で盛んに行なわれ、1983年、ICBD(International Council of Ballroom Dancingの略。国際ダンス評議会。現WDC)が最終決定として、ナチュラル・ターン、リバース・ターン、ナチュラルからのフット・チェンジ、リバースからのフット・チェンジ、ナチュラル・フレッカール、リバース・フレッカール、そしてリバースからナチュラルに切り替えるときのコントラ・チェックと決められた。」 —— なぜフィガー数の調整をする必要があったのか疑問でしたが、「制限をなくすと踊りの特徴が失われる危険があるから」と、リチャード・グリーブさんからお聞きしたことがあります。
・1833年にミス・セルバート(Miss Celbart)が発行した作法の本 <Good Behaviour> には、「既婚の女性は踊っても良いが、未婚の女性が踊るには余りにもふしだらな踊りです」と書かれているようです。知らない男性に抱擁されるような形に不快感を抱いたようです。